見て診て学ぶ 虚血性心疾患の画像診断
−CT・MRI
・
核医学・USで診断する
−
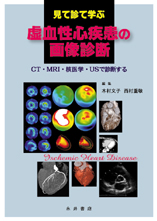
- 著 者
- 編集:
木村 文子(埼玉医科大学国際医療センター画像診断科 教授)
西村 重敬(埼玉医科大学国際医療センター心臓内科 教授)
- 発行年
- 2009年3月
- 分 類
- 仕 様
- B5判・372頁・271図・写真396・35表
- 定 価
- (本体 14,700円+税)
- ISBN
- 978-4-8159-1832-3
- 特 色
- 非観血的心血管画像診断法の各種検査法の概略を素早く学びたいと望んでいる循環器医,循環器を専攻したいと考えている若手医師や放射線診断学や核医学を学び始めた方々を対象に,今後臨床画像検査で主流となる統合画像診断時代を見据え各検査の特徴,適応,比較などをわかりやすく解説した虚血性心疾患の画像診断法のテキスト.
統合画像診断時代では,循環器医,放射線医,診療放射線技師,放射線物理士などが協力し,形態と機能の両面からの疾患,病態の評価が必要とされる.循環器医にとっては基礎的原理,撮像法,画像構成法を,放射線医には画像診断以外の知識を,それぞれ一定水準の知識をもてるようにバランスよく解説.各検査法の特徴がよく理解でき,臨床的根拠に基づいて目的にあった検査の適切な選択ができるようになっている.
虚血性心疾患における画像診断を用いた診断戦略決定のためにぜひお役立ていただきたい.