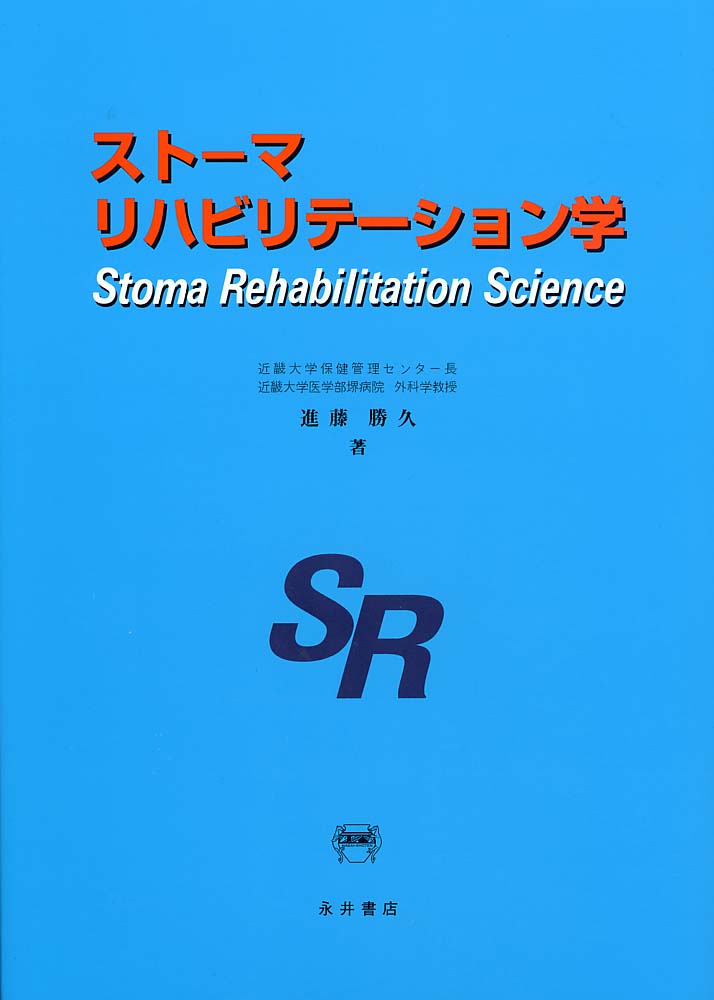ストーマリハビリテーション学
- 著 者
- 著:進藤 勝久(近畿大学医学部堺病院外科 教授)
- 発行年
- 2007年3月
- 分 類
- 消化器外科学
- 仕 様
- B5判
- 定 価
- 定価 9,450円(本体 9,000円+税5%)
- ISBN
- 978-4-8159-1779-1
- 特 色
- 「ストーマ」という用語をはじめて提唱し.ストーマ保有者のそばで感じ,学び,悩んだ,その生きた経験を教材に,ストーマリハビリテーション学にかける40年間の思いを一冊に凝縮した著者渾身の書.
解剖や法律など教科書的な記述ではなく,病気の本質とは,患者中心のケアとは,人間として向き合う医療教育とは,患者をとりまく社会全体の取り組みとは,ストーマリハビリテーション学の課題と将来展望を俯瞰し,全体像をとらえ,学問としていかに昇華させるかを細やかに解説する.また,著者はストーマ手術とケアを解説しながら,同じ外科医に対して手術の結果とアフターケアという,外科医としての責任の自覚を求めているのである.
全人的医療者を目指す外科医,そして看護師にぜひ読んでいただきたい.
序 文
1971年秋に大阪の人工肛門患者会「友起会」でストーマと言う用語を提唱し,リハビリテーション医療で術前と同様に社会復帰できると激励して35年が過ぎた.そのような概念をもった用語は当時の医学界には存在していなかったので,まずは医師に理解してもらおうと書籍原稿を書いた.しかし,無名の若造に耳を傾ける同僚も出版社もなかった.それではと看護師用に書き直して看護出版社に持っていったが,ここでも断られた.当時の医学界はトップダウン式に認められていく世界であった.それではと,世相に逆行する方法を展開,つまり,まずは患者教育をして,看護師が自分の知識と技術のなさに気付いたところで看護師教育を進め,最終的には医師が患者の社会復帰を目指した手術をするようになるという,遠大な計画に切り替えた.その第一歩が患者用に改変して出版された「ストーマリハビリテーション」(1974年)なる著書であった.
幸か不幸か西洋から粘着装具(袋)が輸入されるようになり,西洋でET教育を受けて来る者が現れるようになり,ストーマ関連の研究会や講習会が行われるようになった.ストーマ保有者の社会福祉制度もでき,参考書や雑誌も多く出版されて,確かに開花して,今や外科医の関心もみられるようになった.しかし,装具にしても教育にしても西洋文化の横流し/模倣であるように思えるのは私の偏見であろうか.医療の現場でも職業が分化して,それぞれの専門性を強調するのは効率的でよいことであるが,東洋的な協調,職種連携,共働*は患者の傍に仕える者としては不可欠な要素ではないであろうか.そのためには知識や技術の相互理解の上に立って,一つの心を形成することが重要である.医師と看護師との関係を車の両輪,貨幣の裏表,地球の空海の如くと言うだけでは不十分で,車の目的地と運転,貨幣の対象物と支払い,地球の自然物と保存が問われるのと同様である.
さらにストーマリハビリテーションを学問として育てないと,真理に基づいた発展は期待できない.ストーマの医療,関連する基礎医学,リハビリテーションの理念,関連する社会資源,ストーマリハビリテーションの現場,関連する環境などをよく観察し理解することから始めなければならない.それらを学習する根本には外科医の責任ともいうべき自覚を求めたい.手術は外科医にしか許されていない芸術作品のようなものであるから,製作は最高のもの(命)でありたいし,製作後も自分の命と思って面倒を見たいものである.それはストーマ自体のみならず,その保有者個人やその周辺の方々へも波及する寛大なアフタケアであってほしい.そのような責任感ある外科医ならびに看護師へ本書を捧げる次第である.一緒に学問を進めようではありませんか.
平成19年2月
近畿大学保健管理センターにて
進 藤 勝 久
■ 主要目次
1.ストーマリハビリテーション学問論
1 ストーマリハビリテーション体系化や学問の意義とは
2 学問の方法とは
3 考察しておきたいことは
2.リハビリテーション原論,障害と人権
1 ストーマとは
2 ストーマ保有者人権とは
3 リハビリテーションとは
4 障害とは
5 QOLとは
6 ADLとは
3.障害心理,人間関係,成人学習(患者教育)
1 障害心理
2 人間関係
3 成人学習(患者教育)論
4.ストーマ医療教育論
1 教育原論
2 ストーマリハビリテーション教育
3 地域講習会(初級)
4 リーダーシップコース(上級)
5 WCETストーマ療法看護教育プログラム(ETNEP)
6 日本看護協会認定WOC看護研修
5.組織システム論
1 システム原論
2 医療現場論
3 患者会(オストミークラブ)
4 医療界
5 学 会
6 業 界
6.排泄社会学,ストーマ関連法制学,流通/医療経済学
1 排泄社会学
2 ストーマ関連法制学
3 流通/医療経済学
7.ストーマ装具の人間工学,医工学,ヒューマンインターフェース
1 人間工学
2 医工学
3 ヒューマン(ユーザー)インターフェース
8.排泄・上皮概論
1 排泄とは
2 上皮発生学から見た排泄器官の差異
3 上皮のバリア機能と上皮状態の評価
4 物質代謝から排泄物生成まで
5 細菌学的にみた排泄器官の特徴
6 神経/内分泌系反応と排泄機能
9.排泄制御学,排泄障害概論
1 制御性/禁制と失禁/排泄困難の概念
2 人工肛門における制御性と術式
3 制御性人工肛門の管理理論
4 体外人工臓器の条件
5 尿禁制代用膀胱の場合
6 排泄障害
7 神経因性膀胱
8 直腸肛門機能障害(神経因性肛直腸)
9 排泄障害の原因と病態生理
10 排泄障害の診断方法とアセスメント
11 排泄障害の治療法と管理法
12 排泄障害に対する精神的支援
10.上皮修復概論
1 上皮障害の概念とその機構
2 上皮障害の種類と程度
3 閉塞性環境下での創傷変化/反応
4 上皮管理の可能性
5 上皮の炎症理論
6 治癒機構と治癒因子
7 感染創の治癒過程
8 清潔と消毒と上皮障害性
9 創傷治療原論
10 創傷被覆材の種類と効果
11 瘻孔の種類と管理方法
12 医療用粘着テープの特徴と皮膚障害
11.排泄管理とストーマ管理
1 排泄管理の理念と意義
2 排泄管理の訓練
3 排泄法の原理と適応
4 排泄管理法変更の適応/不適応
5 経年的変化と各排泄法の長期管理
6 ストーマ管理
7 ストーマ管理困難;原因と対策
8 特異的管理
12.排泄音・臭気学
1 人に言えない悩みと外科医への要望
2 におい/音の原理
3 消臭/消音の類似語
4 におい/音 感覚の解剖生理
5 におい/音の心理効果
6 におい/音の発生
7 臭いを発生する物質
8 減臭/減音の原理
9 におい/音の軽減方法の実際
10 におい/音の測定法
11 におい/音の予防方法
12 排泄音・臭気学の医療への応用
13.ストーマ診療学
1 病歴,病状の問診
2 腹部一般所見
3 ストーマの解剖生理
4 ストーマ所見
5 診察記録
6 ストーマ周辺検査
7 治療計画
8 治療評価
9 ストーマ合併症の分類
14.継続医療概論(ストーマ外来,在宅ケア)
1 継続医療の必要性
2 継続医療の施設間連携と職種共働
3 ストーマ外来
4 訪問看護(在宅ケア)
5 退院困難
6 緊急時体制
7 ストーマ リハビリテーションの社会医療システム
8 障害者手続き拒否への対応
15.小児特論
1 小児疾患
2 小児ストーマ造設の留意点
3 ストーマ保有児特有の問題と対応
4 ストーマケアの特殊性
5 小児ストーマ合併症と対策
6 ストーマ閉鎖後の問題点とケア
7 障害心理学
8 関連法制
16.性機能障害・性学概論
1 セクシュアリティの概念と性の多様性
2 性生活の意義
3 男性の性反応(生理学的症状)
4 女性の性反応(生理学的症状)
5 アプローチとアセスメント(性外来)
6 性機能変化の原因と対策
7 ストーマ保有者と相方の性感情や相互関係
8 術後男性の性機能障害の治療とケア
9 術後女性の性機能障害の治療とケア
10 性カウンセリング
17.ストーマ用品学,関連商品論
1 ストーマ用品学
2 失禁用品学
3 商品論
4 用語の相違点
18.ストーマ手術学
1 造設位置マーキング
2 単孔式人工肛門造設術(永久的消化管排泄孔変更手術)
3 双孔式人工肛門造設術(一時的消化管排泄孔変更手術)
4 人工肛門閉鎖術
5 器械吻合性人工肛門造設・閉鎖術
6 新直腸肛門造設術
7 尿路変更手術
8 ストーマ修復術