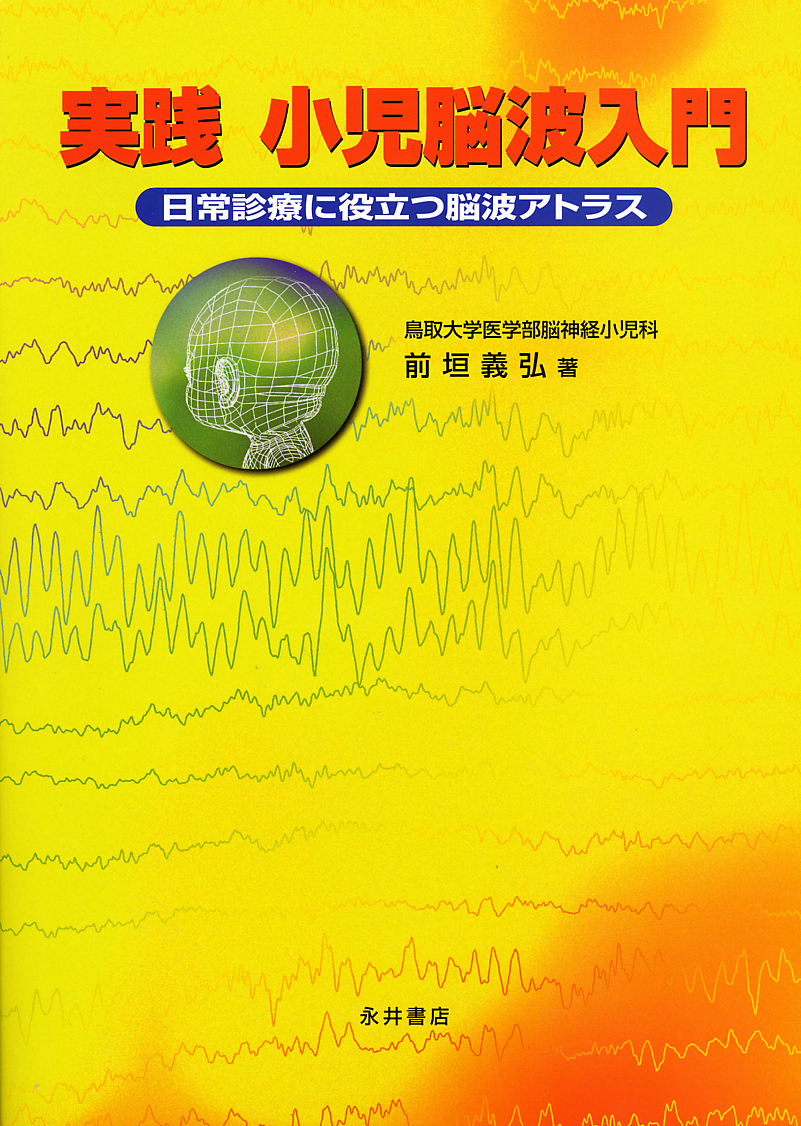実践 小児脳波入門 日常診療に役立つ脳波アトラス
- 著 者
- 著:前垣 義弘(鳥取大学医学部附属脳幹性疾患
-
- 研究施設脳神経小児科学 講師)
- 発行年
- 2007年2月
- 分 類
- 小児科学
- 仕 様
- A4判
- 定 価
- 定価 6,300円(本体 6,000円+税5%)
- ISBN
- 978-4-8159-1778-4
- 特 色
- 小児神経の専門医ではない小児科医,研修医,医学生を対象に,難解と思われがちな小児脳波について,これだけ知っておけば十分と思われる脳波所見に絞って詳述した実用書.
実物大の脳波を同一の脳波モンタージュで提示し,Commonな疾患と重要な疾患や,てんかん波と間違いやすい正常脳波やアーチファクトについて詳述する.従来の教科書とは異なり迷いやすい脳波所見を数多く収載し,用語解説,参考資料,診療上の重要ポイントを記載するなど,日常診療での脳波解読の基本的な考え方や診断・治療について実践的な力となる良書.
序 文
はじめに
小児神経領域は幅が広く専門的であるため、小児科医にとって苦手意識が強いようである。このような状況から、平成15年より鳥取大学小児神経学入門講座を開催するようになった(情報はホームページに掲載http://www.med.tottori -u.ac.jp/dcn/)。発達障害や知的障害、てんかんなど小児科医が診療する頻度の高い疾患の基本的な考え方や診断・治療についての実践的なレクチャーを行っている。脳波は、必要性は高いが判読が難しいと感じる小児科医が多い。教科書を読んだり講義を聴いてすぐに脳波を判読できるようになるというわけではない。小児神経学入門講座での脳波レクチャーは、“2時間で正常脳波とよく見る小児てんかんの脳波が読めるようになる”ことを目的に、5人程度の少人数で実物の脳波を1頁ずつめくりながら解説する予定であった。しかし、希望者が多く講義形式にせざるを得なくなったため、脳波をコピーして講義資料を作成した。本書は、この講義資料をもとに解説をつけてまとめあげたものである。
小児の約10%はなんらかの原因でけいれんをきたすとされる。そのすべてを専門医で診てゆくことは不可能である(小児神経科専門医は約1,000名であり、てんかん専門医は300名に過ぎない)。小児の発作性疾患のうち、熱性けいれんや予後のよいてんかんが大部分を占める。これらcommonな疾患は、専門医でない小児科医が診ていることが多い。本書は、専門医でない小児科医、研修医、あるいは医学生が、これだけ知っておけば十分であるという内容で構成している。すべてについて網羅している教科書ではなく、日常診療に必要なことが詳述してある実用書である。できる限りわかりやすく実際的な内容にしたつもりである。本書の特徴をまとめると以下のようになる。
1・実物大の脳波を同一の脳波モンタージュで提示:ほとんどの教科書の脳波は縮小している。初学者にとって縮小された脳波と実物とのギャップは大きい。本書は実物大の脳波を提示している。また、脳波モンタージュが異なると理解が難しいので、統一して表示した。
2・Commonな疾患と重要な疾患を詳述:てんかんは種類が多く脳波も多様であるが、commonな疾患に的を絞ると理解しやすい。急性脳症は、高頻度ではないが熱性けいれん重積との鑑別が重要である。
3・てんかん波と間違いやすい正常脳波やアーチファクトについて詳述:小児てんかんの脳波異常は、高振幅ではっきりしている場合が多いので見逃すことは少ない。むしろ、正常脳波や normal variant、アーチファクトをてんかん波と間違えることの方が多い。
私は鳥取大学脳神経小児科で研修を行い、自分で脳波を記録する中で、アーチファクトと脳波の違いを経験的に学習した。竹下研三先生や大野耕策先生の指導のもと、良性てんかんから難治性てんかん、急性脳症に至るまで幅広く勉強させて頂いた。また、てんかん患者の、診断から治療終了までの長期経過を多く診させて頂いた。その中で局在関連性てんかんの脳波経過と臨床経過は相関しないことや、典型的な脳波異常にも幅があることなどを学んだ。教科書にはすべて記載されているが、典型的な脳波以外は示されていない場合が多い。迷いやすい脳波所見を本書では数多く掲載した。まずは、各脳波所見を覚えようとせずに、一つひとつ確認しながら全体を通読して頂きたい。実際の症例にあたったときに再度読み見直して頂ければ、理解しやすい。典型的な症例を2〜3例経験すれば、その後は容易となるであろう。
本書を作成するにあたって、河原仁志先生からのご提案で、臨床面での重要な点を“診療のポイント”として入れたので参考にして頂きたい。最後に、貴重なコメントを頂きました、辻 靖博先生と梶 俊策先生、小倉加恵子先生、栄徳隆裕先生、本書の出版をご提案・ご推薦頂きました、大野耕策先生に厚く御礼申し上げます。
平成19年2月吉日
前垣義弘
■ 主要目次
● 用 語
Ⅰ 小児の発作性疾患と脳波
1.小児発作性疾患
2.てんかん診断における脳波の役割
3.てんかんの経過と脳波変化
4.熱性けいれんと急性脳症
5.てんかんと間違われやすい発作性疾患
6.病的意義のない脳波異常
II 脳波の基本的事項
1.電極配置と名称:10-20電極法
2.脳波導出法
3.脳波の要素
4.脳波異常
III 正 常 脳 波
1.覚醒―睡眠サイクルと脳波:各stageでみられる脳波所見
2.年齢ごとの正常脳波
3.賦活脳波
IV 頻度の高い小児てんかんと急性脳症の脳波
1.中心側頭部に棘波を示す良性小児てんかん(BECTS、ローランドてんかん)
2.特発性小児期後頭葉てんかん(ICOE)
3.欠神てんかん
4.点頭てんかん(West症候群、infantile spasms)
5.細分類不能の局在関連性てんかんと内側側頭葉てんかん
6.急性脳症・脳炎と熱性けいれん重積
V てんかん性異常波と間違えやすいnormal variant
1.熱性けいれん児にみられる非定型棘徐波(pseudo petit mal)
2.6Hz棘徐波複合(phantom spike)
3.6Hz陽性棘波、14Hz陽性棘波(14 & 6Hz陽性棘波)
VI よく見るアーチファクトと耳朶電極の活性化
VII 脳波記録時の心電図からわかること
1.不整脈や心伝導障害
2.脳波に混入した心電図や脈波の鑑別
3.体動やミオクローヌス
参 考
1● 瘤波とK複合波
2● 睡眠導入剤の使用
3● BECTS関連疾患
4● 後頭部突発波とPOSTS
5● 不随意運動のミオク ローヌスとミオクロニー発作
6● 脳波オーダーのポイント
7● 脳波レポートの1例
診療のポイント
1● 初発発作の解釈と治療
2● てんかん治療における脳波検査の意味
3● 発作症状からてんか ん症候群を推定するポイント
付録 脳波スケール